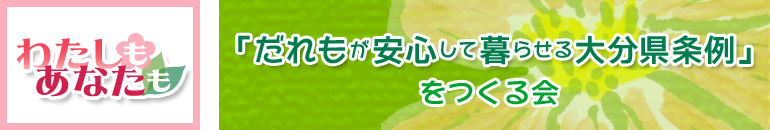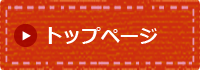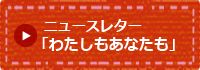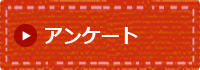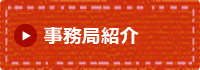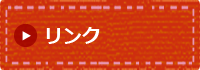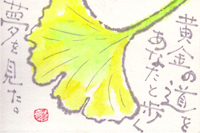条例成立後は「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」として条例に込められた願いの実現をめざして取り組みを続けています。
関連する取り組みについては以下のホームページをご覧ください。
JR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページ
優生保護法裁判を支援する大分の会のホームページ
JR駅無人化反対訴訟第13回口頭弁論の報告
意見陳述に立った徳田靖之弁護士は、先頭に立って訴えてきた故吉田春美さんが裁判に込めた思いと津久見駅事故で亡くなった視覚障がいのある女性の無念さを忘れないでもらいたいと訴えました。その上で、障がいがある人だけに事前調整を求めることの差別性、「津久見駅事故は駅員がいても防げなかった」と責任逃れのための主張を繰り返すJR九州の背信性を批判。今後の審理で解明されなければならないことは、JR九州の公益性とその主張の真実性、正当性だと指摘しました。
松尾康利弁護士は、報道されてきた「被害者がホーム上に這い上がろうとしていた」という運転士の言葉に関連して、JR九州による聴き取りの報告を明らかにするよう求めました。JR九州はこれまで、運転士の言葉については「新聞記事に書いていたが、本当がどうかわからない」としており、聴き取りをしたことすら明らかにしてきませんでした。ところが昨年12月18日付の被告側陳述書には「(九州運輸局から)運転士からの聴き取りをするよう要請を受けた」とあります。事故の状況を把握し原因究明するためには不可欠の対応です。松尾弁護士は「九州運輸局に、運転士がどのように説明したと報告したのかなどわかる証拠を出してほしい」と求めました。
JR九州側は即答しませんでした。また、弁護団が求めている青柳前社長の証人尋問についてもJR側は反対しており、裁判所は今後の証人尋問の結果によって判断することになりました。
引き続き行われた報告会では、原告から「JRを利用したくてもできない人がたくさんいるのが現実だ」「津久見駅事故でJR九州が被害者の責任であるかのように主張していることがおかしい」「JRは人が亡くなった津久見駅で一切対策をしておらず不誠実だ。これ以上私たちを無視させないという気持ちで力を合わせて臨みたい」というお話がありました。
徳田弁護士は、2月13日、3月6日、5月15日に行われる証人尋問について、「5月15日までにはこの裁判の行く末が決定すると思っている。山場は3月6日になる」と話し、支援を呼びかけました。
次回口頭弁論は2月13日(木)10時30分から大分地方裁判所で行われます。津久見駅で起きた視覚障がい者の死亡事故を調査したJR九州社員が証人として出廷します。どのような調査を行い、九州運輸局にどのように報告したのか、なぜ転落事故であることを否定しているのかなどについて直接の担当者から説明があり、弁護団から反対尋問が行われます。
その後の予定は、3月6日には原告側の証人尋問、5月15日には被告側の証人尋問が行われることになっています。
「優生保護法裁判を支援する会」が「いのちの選別のない大分の会」へ
当日は「裁判報告会」として開催し、第1部として最高裁判決や新たに制定された補償法について弁護団が講演、第2部として「いのちの選別のない社会へ」をテーマにしたシンポジウムを行い、第3部が支援する会の総会でした。
総会では、課題となっていた裁判終了後の会の新たな名称を「いのちの選別のない大分の会」に決定しました。
そして参加した会員の総意として、被害者全員の救済と優生思想をなくす取り組みをこれからも続けていくことを確認しました。
また、この日に開いたシンポジウムを繰り返し開いて、社会や私たち一人ひとりに根深くある優生思想をなくしていく取り組みを続けていくことなどを確認しました。(シンポジウムの報告は準備中です)
優生手術被害者救済へ「個別通知」 大分県が準備
10月12日の新聞で「(大分県は)県内の被害者に救済制度を直接伝える「個別通知」に向けた準備を始めると明らかにした。8日に手術を巡る補償法が成立したことを受け、対応を決めた」と報道されました。
佐藤樹一郎・大分県知事は、「心身に多大な苦痛を受けてこられた当事者の気持ちを考えると、心が痛む。補償法の成立を受け、県としても個別通知に向けた調査に直ちに着手することにした」というコメントを出しました。
徳田靖之弁護士は「画期的なことだ。新法が成立後、個別通知に向けた動きをするのは全国で大分県が初めて。我々の要求に応えてくれ、高く評価している」と話しています。
報道によると、「県が保有する資料から所在確認などを進め、可能な限り通知に努める」「資料を基に現住所などを市町村に照会し、問題がなければ通知していく」「本人が亡くなっている場合は、遺族に連絡を取る」「各地の医療機関や障害者団体に協力を仰ぎ、資料に名前がない被害者の掘り起こしにも取り組む」などの方針を明らかにしています。
(以上、10月12日付「大分合同新聞」による)
この動きは、補償法の成立による大きな成果です。支援する大分の会や弁護団も被害者の全員救済と優生思想をなくすことをめざして、県の取り組みにも協力していくことを確認しています。
大分地裁優生裁判和解で終結。全員を救済し優生思想をなくす取り組み続く
弁護団は「国がこれまで憲法違反を認めず、20年の除斥期間を主張して補償を拒み続けてきた態度について、反省を示さない限り和解には応じられない」という姿勢で臨みました。
意見陳述に立った徳田弁護士は、最高裁判決が国の責任を厳しく指摘したことを示し、「国が憲法違反の認否をせず、過去の加害行為に蓋をして責任逃れをしてきたことに、明確な反省を示さない限り和解に応じられない」と主張しました。
これに対して国側代理人は、「主張が原告の心を傷つけ、解決を遅らせ、原告に多大の負担をかけたことを反省し謝罪する」と意見表明しました。
この発言を受けて、弁護団は和解を受け入れると表明しました。
裁判長は弁護団の求めに応じて和解条項を読み上げ、原告と被告の双方が受け入れに合意して裁判は終結しました。
直後に行われた報告会で、徳田弁護士は「皆さん勝ちました。全面勝訴を皆さんに報告し、皆さんと一緒に喜べる機会を得ることができ本当にうれしく思います」と喜びを伝えるとともに、「勝ったことの意味を現実にするためにはこれから」と、全国で4番目に多い大分県の被害者に救済を届けるための取り組みへの協力を呼びかけました。 西村務・大分県聴覚障害者協会会長(支援する会共同代表)は、「今日は本当にうれしい」と喜びを述べるとともに、「聞こえないということで、手術を受けて『言えない』という方もいるし、亡くなった方もいる」と現実を指摘。「差別のない、手話も広がった社会をめざしたい」と述べました。 平野亙・支援する会共同代表は、「2万5000人の被害者全員の救済」の重要性を指摘するとともに、「本当の救済は、社会が変わること。障がいがあることや手術を受けたことが恥ずかしいことでも何でもないし、家族にも優生手術は自分たちの罪ではなくて国の政策が間違っていたと伝えていきたい」と話しました。そして優生思想について、「津久井やまゆり園事件で明らかになったように、優生思想は根深い。根底から変えていくのは長く苦しい闘いになるが、それをやっていかねばならない。それをやっていかないと私は安心して娘を残して先に死ぬことができない。皆さんと一緒にこの社会を変えていく、そういう活動をずっと続けていきたいと思います」と述べました。
JR駅無人化反対訴訟第12回口頭弁論は9月5日です
優生保護法裁判第5回口頭弁論(大分地裁)は6月7日です
集合時間は14時10分、入廷行動を14時15分から行います。
口頭弁論は15時からで、終了後には報告会(県弁護士会館)を行います。
今回は、裁判長が代わって最初の口頭弁論になります。意見陳述では徳田弁護士が裁判の全体像について、三宮弁護士が学校教育における優生保護法(優生思想)の影響について述べます。
ぜひご参加下さい。
JR駅無人化反対訴訟第11回口頭弁論は4月25日です
昨年(2023年)10月以来、JR九州側と現地進行協議を巡るやりとりが行われてきましたが、実現が近づいています。
今回の口頭弁論では、無人化された時間帯に起きた津久見駅の視覚障がい者の死亡事故をめぐるJR九州の対応など、駅無人化を巡る様々な問題が論点となります。
進む駅無人化や廃線・バス転換などの動きなかで重要性が高まる駅無人化反対訴訟です。傍聴にぜひご参加下さい。
JR九州に対する署名の取り組みや演劇「無人駅ホームな人々」(4月6日・7日上演)についてはJR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページをご覧ください。
旧優生保護法大分訴訟第4回口頭弁論は3月1日です
13時30分に集合して入廷行動を行いますのでぜひご参加下さい。
裁判所を動かすためにも傍聴が大切だというお話が弁護団からもありました。明らかな憲法違反を認めず、除斥期間を理由に賠償も認めようとしない国に対して、一人ひとりの思いを示しましょう。
12月1日の第3回口頭弁論では、裁判所が国に対して「説明するしないは自由だけど、しない場合、裁判所が不利益に解釈してもかまわないか」と回答を求め、報告会では徳田弁護士から「大きな前進だった」という話がありました。 2月19日には2人目の提訴が行われ、被害を受けた人が声を上げやすくなるようにという願いは一歩ずつ進んでいます。
支援の動きも進み、最高裁に対する署名は大分県で3万5千筆を超え、「優生保護法裁判を支援する大分の会」も参加の呼びかけを開始しています。
皆様のご参加とご協力によって、「生まれてくるすべての子どもたちをぎゅっと抱きしめてくれる社会」をつくっていきましょう。
詳しい報告は優生保護法裁判を支援する大分の会のホームページでお読みいただけます。
「JR津久見駅死亡事故の原因を明らかに」駅無人化反対署名実施中
詳しい報告は、署名用紙、チラシ等はでご覧になれます。(JR駅無人化反対訴訟を支援する会「署名」のページでダウンロードできます)。
旧優生保護法大分訴訟第3回口頭弁論(2023年12月1日)の報告
50人を超す支援者が傍聴に駆けつけたなか、弁護団は、国が憲法違反について認否を明らかにせず、20年の除斥期間を理由に賠償も認めようとしないことを強く批判しました。
意見陳述で岡田弁護士は、国が旧優生保護法に基づいて、障がいがある人たちを「不良な存在」とする優生思想を学校で教育するなどの施策を進め、このような施策によって差別や偏見が固定化され、個人の尊厳が踏みにじられ続けてきたと指摘。それにもかかわらず、国が憲法違反であるかどうかを明らかにせず、20年の除斥期間の適用を主張していることを強く批判しました。
報告会で徳田弁護士は、「旧優生保護法はつくったときから憲法違反という日本の歴史上初めての悪法」と指摘。「全国の裁判所で『憲法違反』という判決が出ているのに国は認めようとしない」と批判しました。
詳しい報告は優生保護法裁判を支援する大分の会のホームページでお読みいただけます。
なお、次回(第4回)口頭弁論は2024(令和6)年3月1日(金)14時から(13時30分集合)です。ぜひご参加下さい。
JR駅無人化反対訴訟 第10回口頭弁論の報告
意見陳述で松尾弁護士は、JR九州の「法令を遵守している」という主張に対して、「法令で義務化されていないから安全対策をしていないというのが実情だ」と指摘。「とうてい、十分な安全対策がなされているとは言えない」と厳しく批判しました。
報告会で徳田弁護士は、現地進行協議によってSSSの問題点などを明らかにするとともに、次回口頭弁論では津久見駅で視覚障がい者が死亡した事故について全面的に主張を展開したいと話しました。
次回口頭弁論の日程はまだ決まっていません。
詳しい報告は「JR駅無人化反対訴訟支援ニュース」第11号でご覧いただけます(JR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページでダウンロードできます)。
「優生保護法裁判に正義・公平の判決を」最高裁に求める署名を開始
被害に対する国の謝罪はなく、補償を受けた人は1割にも達していません。国の責任の明確化と被害に応じた補償を求める裁判は、大分を含む全国12の地裁・支部に提訴され、高等裁判所、さらに最高裁判所でも審理が続いています。
最高裁の判決が大きな意味を持つことから、全国の裁判を支援している優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)は最高裁に提出する署名を開始しました。大分でも全力で取り組みます。
署名用紙は こちら、署名呼びかけチラシはこちら でダウンロードできます。ぜひご協力をお願いいたします。
旧優生保護法被害裁判を支援する会(大分)のホームページはこちらでご覧になれます。
9月29日に旧優生保護法被害国家賠償請求訴訟の第2回口頭弁論
12時50分に集合して13時から入廷行動を行い、14時傍聴、終了後は報告会を行う予定です。
ぜひ傍聴しましょう。
「優生保護法を考える市民の集い」(2023年9月24日)のご案内
今年6月に大分で旧優生保護法による強制不妊手術の被害を受けた方の裁判が始まりました。
旧優生保護法は1996(平成8)年まで48年間、全国で約2万5千人の障がいのある方に不妊手術を強制してきました。大分で被害を受けた人は746人に上るとされています。
高齢化してきた被害者に対するお詫びと補償は遅れています。裁判を通して1日も早い補償を実現しなければなりません。
同時に、「生まれていい命」と「生まれてはいけない命」の選別を国が進めてきたことが、私たち一人ひとりの間に相模原事件にもつながる根深い差別意識を広げてきたことを反省しなければなりません。
私たちは、どうすれば障がい者差別をなくすことができるかを一緒に考えたいと思いました。
その最初の取り組みとして、9月24日に大分市のソレイユで「優生保護法を考える市民の集い」を開きます。
不妊手術を強制された障がい当事者のお話、弁護団による法律や裁判の説明、障がい当事者を中心にしたリレートークなどを予定しています。
被害を受けた人たちと市民が一緒に声を上げ、一緒に考える場を持つことは、差別をなくすための大切な一歩になるものと考えています。
ぜひご参加ください。
日時 9月24日(日)15時30分
場所 大分市中央町 ソレイユ 7階 アイリス
集いの詳しい内容は チラシ(PDF)に掲載しています
- のでご覧下さい。
- ニュースレター「わたしも あなたも」最新号(第15号 2015年9月15日発行)(こちらでご覧ください)
なお、9月29日(金)には大分訴訟の第2回口頭弁論が大分地方裁判所で行われます(13時50分集合・15時傍聴・終了後報告会)。可能な皆様はぜひ傍聴にご参加下さい。
「旧優生保護法被害裁判を支援する会」(仮称)準備会
(連絡先 だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会)
「JR駅の無人化に反対する市民集会」(2023年7月16日)の報告
「当日の時間変更を断られた」「利用駅が午後無人化されたために病院を変えざるを得なかった」「SSSのボタンが届かなかった」「車いすで使えるSSSはなかった」「鉄道は対面サービスがどんどん低下している」という当事者の体験。「視覚障がい者の声が始めて法廷内に届いた」「全国に広がる無人化の動きに一石を投じた」と裁判に共感する声。JR社員も参加し、「国鉄改革を36年前に経験したが、利益を上げるためにやったわけじゃない。利益を上げて、公共交通を守るために国鉄改革をやった」と証言しました。
オンラインで参加した木村英子参議院議員は、「電車に乗りたくても、駅員を呼ぶためのインターホンが使えずに駅を利用しづらかったり、駅員が遠隔地から来るためにかなりの時間待たされたり、事前の予約がなかったら電車に乗せてくれなかったり、様々なバリアがあって昔よりも電車に乗ることが困難になっている」と問題点を指摘。「誰もが当たり前に駅を利用するという権利から障がい者が排除されている現状は、差別解消法とは逆行している。公共交通機関による移動の権利が、障がい者も当たり前に保障されるように、粘り強く皆さんと一緒に闘っていきたい」と話しました。
弁護団からは平松弁護士が、「裁判では、①JRの公共性②障がい者の不利益③JRの負担の重さ-が判断の要素。第1に、公共交通を担うJRは一般的な民間企業より厳しく公共性が問われる。第2に、障がい者は駅無人化によって事前の予約や調整が求められ、命に関わる危険も増す。第3に、JR九州は3877億円の調整基金など国から様々な優遇を受け、しかも2022年度は311億円の黒字。駅無人化をこれほど拡大するのはひたすら利益拡大のためで、障害者差別解消法が求める合理的配慮の提供に反する」と裁判の争点について報告。
徳田弁護士は、JR津久見駅で起きた視覚障がい者の死亡事故について、「事故の原因を明らかにした上で再発防止策を明確にするようJRに求めたが、原因も対策も全く明らかにしていない」とJR九州のあり方を批判。裁判では、「会社の利益のためには、障がいがある人たちの貴重な命が奪われても何とも思わないのか、そういう企業が許されるのかを問わなければならない」と話しました。
その上で、「JR九州が赤字だから駅無人化は当然」という声について、「JR九州は民営化以来、赤字になったことがほとんどない。毎年多額の黒字を計上し、株主には多額の配当をしている。去年は、コロナの影響を脱して311億円もの黒字。鉄道部門も31億円の黒字」と話しました。そして、「障がいのある人の命が危険にさらされるなか、これだけ利益を上げながらさらに無人の駅を拡大するということが許せない」と裁判を闘う意義を話しました。
今後の取り組みについては、平野・共同代表が「公共性とは何かがこの裁判では問われている。公共のネットワークは使える状況になければ存在しないと同じ。JRは使える路線でなければならない」と指摘した上で、「視覚障がい者の立場から釘宮さんが原告に加わり、安全性の問題が具体的な争点になったことを受けて、もう一度署名に取り組みたい。署名活動を通して、九州各県に原告を増やしたい。取り組みの基本はみんなで傍聴に行くこと。裁判官には、当事者の苦しみを本当に理解して、人間として見てほしい。裁判を通じて国の政策に影響を与える可能性を広げたい。一緒に頑張りましょう」と呼びかけました。
最後に司会の松尾弁護士が、「JR九州は津久見駅の死亡事故から半年経っても、公式な裁判の書面に『報道によると被害者の方は立ち入り禁止区間にも入っていたらしい』ということを書いている。自分が管理している駅で起きたことについて、『報道によると』という言い方で、まるで立ち入り禁止区間に入ったから悪いんですよと言いたいかのような書面を今の時点でも出していることに怒りしか覚えない。皆さんのご参加、ご意見を活力にしながら、しっかり反論して闘っていきたい」とあいさつし閉会しました。
詳しい報告は「JR駅無人化反対訴訟支援ニュース」第10号でご覧いただけます(JR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページでダウンロードできます)。
JR駅無人化反対訴訟第9回口頭弁論(7月6日)の報告
徳田弁護士はJR九州の背信性について、①裁判係争中に駅無人化を拡大②津久見駅事故の原因も再発防止策も示さず駅無人化を拡大③巨額黒字に転じたのに駅無人化を拡大④駅無人化の範囲が拡大しSSSや拠点駅構想では対応が困難―と指摘。これらの点を明らかにするために、拠点駅とされる大分駅(SSSを含む)・亀川駅等で現地進行協議を行うよう求めました。
JR駅無人化反対訴訟の第9回口頭弁論は2023年7月6日。7月16日には反対集会
第3次提訴も併合されることになり、訴状の陳述と新原告による意見陳述が行われる予定です。視覚障がいの方が駅無人化によって危険に直面していることなどを訴える重要な場になります。12時50分に集合して13時から入廷行動を行い、口頭弁論終了後に報告会を行います。
7月16日(日)には、安全性を争点に加えた裁判の現状を共有し、津久見駅死亡事故をみんなの問題として広く訴える「JR駅の無人化に反対する市民集会」を大分市のホルトホール大分で15時から開催します。
駅の無人化や地域路線の存廃の動きが強まるなか、障がいのある人と地域、そして全国の皆さんと力を合わせて、公共交通を守る動きを強めていくことをめざしています。
大分県では昨年12月にJR津久見駅で無人化された時間帯に視覚障がい者の死亡事故が起きました。しかし、JR九州は事故原因も防止対策も明らかにしないまま、駅の無人化をさらに進めています。黙ってみてることはできません。
利用者に不便と危険を強い、自治体に負担を押しつけるJR九州の問題点を様々な角度から明らかにし、駅無人化をみんなの問題として考え、全国にも発信します。ぜひご参加ください。
オンライン参加もできます。ご希望の方は info@daremoga-oita.net までメールでご連絡ください。
旧優生保護法被害国家賠償請求訴訟第1回口頭弁論(6月16日)の報告
16日の口頭弁論後の報告会で弁護団は、「違憲性はだれの目にも明らか。国は争点を“除籍”に絞り本質から目をそらす態度だ」、「悪法を放置し、誤った考えにより被害を広げた国の責任は大きい」と指摘しました。
私たちの生活に大きな影響を及ぼす国の姿勢を変えるために、私たち一人ひとりが声を上げることが重要になっています。この裁判を支えるために裁判を支援する会を立ち上げる予定です。
大分で6月16日に旧優生保護法被害国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁論
「不良な子孫の出生を防止する」という差別的な考え方によって子どもを産むことができなくされた事実を共有し、障がいのある人たちが偏見に苦しんできた現実を心に刻み、被害者を救済するとともに差別をなくしていくための重要な取り組みです。
ぜひ傍聴しましょう。
JR駅無人化反対訴訟第3次提訴を行いました
昨年3月12日にJR九州が九州全域で無人駅を拡大した際に、釘宮さんが利用する坂ノ市駅を含む多くの駅で無人の時間帯が増やされました。このため、視覚障がいのある釘宮さんは切符の購入が困難になり、掲示板や貼り紙での情報の周知にも接することができず、電車の遅延情報等やホーム変更等の情報を教えてもらうこともできなくなりました。さらに安全の面において、駅員の見守りがなくなり、転落した場合でも対応してもらうことができなくなりました。釘宮さんは「人がいないと視覚障がい者は落ちたらそれで終わり」と不安を話しました。
無人化された駅では、視覚障がい者は、従来のようにいつでも自由に駅を利用をすることができなくなります。事前の予約が必要になります。これは障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の不提供にあたるのではないかというのが一つの重要な争点です。そして今回の提訴で加わったもう一つの重要な争点が「安全性」の問題です。これからの裁判は「合理的配慮」と「安全性」という二つの争点を巡って展開されていくことになります。
JR駅無人化反対訴訟第8回口頭弁論の報告
福山さんは、12月15日にJR津久見駅で起きた事故で亡くなられた視覚障がい者に哀悼の意を表し、「JR九州は、障がい者に優しい本来の姿に戻って、駅の無人化を直ちに撤回してほしい」と訴えました。
松尾弁護士は「障がい者に合理的配慮を提供してきた駅員を削減したJR九州は、コストカットのための人員削減によって安全性を低下させているのではないか」と意見陳述で指摘しました。
詳しい報告は「JR駅無人化反対訴訟支援ニュース」第9号でご覧いただけます(JR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページでダウンロードできます)。
津久見駅死亡事故-JR九州に原因究明と再発防止を要請
地域の公共交通を担う重要な企業としてご尽力されておりますことに敬意を表します。
私たちだれもが安心して暮らせる大分県をつくる会は「障がいがある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」の制定を目指してつくられた障がい者・家族と県民の会です。2016年に大分県議会で全会派の賛同により条例が制定されて以降は、条例に込められた障がい者や家族の思いを地域で実現するために活動を続けています。
昨年12月15日に津久見駅で発生した痛ましい死亡事故について、二度とこのような事故が起きないよう徹底して事実関係を明らかにし、原因を解明することを求めて要請を行います。
2017年の貴社による大分市内8駅の無人化計画の発表は、条例の実現や法律の改正によって社会参加が進むという期待を抱いている障がい者やその家族にとって受け入れがたいものでした。「利用しにくくなる」「危険になる」「事故が起きたら誰が助けてくれるのか」という声は切実でしたが、無人化計画はさらに拡大されています。
津久見駅で起きた事故は、私たちが抱いてきた不安が現実になったものにほかなりません。事故で亡くなられた方は視覚障がい者であり、事故は駅員がいない時間帯に発生しました。事故の原因はまだ明らかにされていませんが、現時点で言えることは、駅員がいれば危険な場所にいる人に声をかけたり、ホームからはい上がろうとする人を見つけ救出する可能性があったのではないかということです。
駅ホームにおける視覚障がい者の転落事故は数多く発生しており、国土交通省が設置した「新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会」の中間報告(令和3年7月2日)は「10年間(平成22年度~令和元年度)の年間平均発生件数は74.7件」というデータを示しています。この中間報告で、転落防止に「最も有効」とされているのは「ホームドアの整備」ですが、加えて「非常に有効な視覚障害者のホーム転落防止策」として「駅係員及び周囲の鉄道利用者等による直接の誘導案内、声かけ、見守りである」と明記しています。一方、AIカメラやスマホアプリ等による安全対策については「現時点では、アプリによる案内と利用者の歩行ルートの不一致等により転落に繋がる危険性が排除できない」等の問題を指摘し、技術的に確立していないことが明らかにされています。この中間報告を踏まえても、駅を無人化することが視覚障がい者の危険性を増大することは明らかだと言わざるを得ません。
私たちは、津久見駅で実施された駅の無人時間帯の拡大が、救える可能性があった命を救えなくした可能性を指摘し、一方的に無人化を拡大する貴社の姿勢に強く抗議します。また、このような事故を再び起こさないために、以下の点について要請します。
1,津久見駅における死亡事故発生について原因を明らかにするとともに、責任を明確にし、再発予防の対策を取ること。
2,駅の無人化を進めたことが事故の重大化につながった可能性を踏まえて、これ以上の無人化を止めること。
3,JR九州は、障がいについての理解と障がい者に対する必要な対応について学習し、障がいがある人たちの声に基づいて旅客サービスのあり方を全面的に見直すこと。
JR駅無人化反対訴訟第8回口頭弁論は12月28日に行われます
日時 12月28日(水)午前11時から
場所 大分地方裁判所
(当日は入廷行動を9時50分から行う予定です。傍聴券の配布は10時頃からと想定しています。)
今回の口頭弁論では、9月15日に行った第2次提訴が併合されて、訴状の陳述と新原告による意見陳述が行われる予定です。
「駅が無人化されると利用が困難になる」「安心して乗れなくなる」という声を無視し、鉄道部門の赤字を強調してさらに“効率化”(駅無人化拡大、自治体への負担転嫁等)を押しつけてくるJR九州に対して、公共交通の要としての役割を果たすよう主張していく場になります。
「吉田春美さんを偲ぶ会」が開催されます
JR駅無人化反対訴訟原告団の先頭に立って頑張ってこらた吉田春美さんは9月14日、がんのため69歳で亡くなられました。
若いときから町のバリアフリー化など様々な取り組みを行ってこられ、その延長線上にJR駅の無人化問題への取り組みもありました。
様々な時代、様々な場面で吉田さんと一緒に行動してきた方々や吉田さんに共感してきた方々が集まり、みんなでゆっくりと吉田さんとの思い出を語り合う場になります。
日時 11月27日(日)13時~16時
場所 大分市 ワークスペース樫の木
詳しい内容や申し込み方法などはJR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページ(発行物のページ)でご覧いただけます。
JR駅無人化反対訴訟第7回口頭弁論の報告
JR九州は、プレゼンテーションで鉄道事業の赤字などを説明し、「情勢は厳しい」として駅無人化などの「生産性向上が必要」と主張するとともに、「十分な合理的配慮をしている」と主張しました。
原告側の徳田弁護士は、JR九州が「公的に多額の援助を受けている」ことを認めたことを指摘し、一方で「高額な株主に対する配当(今年度146億円の予定)を行い、役員報酬も3億7900万円支払われている」ことを指摘しました。
また、JR九州が裁判で提出した「JR九州完全民営化プロジェクトチームとりまとめ」のなかに、「JR九州は自社の鉄道ネットワークが果たしている意義・役割を再認識し、今後の九州地域の発展及び活性化に向けて、不採算路線も含めた必要な鉄道ネットワークの維持とともに、サービスの向上、(中略)バリアフリー化の推進、防災対策の強化等の鉄道ネットワークの更なる発展を進めていく必要がある。また、鉄道事業者にとって最も重視されるべきは、安全性の確保である。(中略)引き続き国民の安全・安心や生活の足を守るという観点から、安全設備等への投資をおろそかにせず、必要な安全レベルを確保していかなければならない」という記述があることを指摘。
徳田弁護士は「この記述は原告らが主張してきた内容そのもの」であり、「駅無人化は、障がいを有するものにとっては、鉄道ネットワークの廃止や縮小であり、また、安全の低下です」と主張しました。
会報等をJR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページでご覧いただけます。
JR駅無人化反対訴訟第7回口頭弁論は9月29日に行われます
JR駅無人化反対訴訟第2次提訴を行いました
訴状では、今年3月12日にJR九州が駅の無人化を拡大したために事前の予約が必要になり、自由にJRを利用することができなくなったことから、駅無人化が障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の不提供にあたると主張しています。
さらに、JR九州の鉄道部門だけを切り離した赤字を理由とする主張に対して、JR九州には「3800億円もの巨額の税金の投入」など莫大な公的支援がなされており、鉄道部門の運営にあたっては「公益性を重んじて、国民の利益に奉仕し続けることが義務づけられる」と指摘しています。
提訴後の記者説明で徳田弁護士は、「鉄道部門は赤字と言いながら、全体では数百億の利益を上げ、高額の配当を続けていることが明らかになった。それにもかかわらず無人化の範囲を広げた」とJR九州の姿勢を批判しました。
原告の福山さんは「JRに乗るといろんな人に出会え、お話しできるので大好きです。駅が無人化されると出かけにくくなり、行動範囲が狭まってしまうので無人化にはしてほしくないなと思います。いろんな方がJRを使いやすくなるようにしてほしい」と話しました。
JR駅無人化反対訴訟第6回口頭弁論の報告
多くの皆さんが傍聴するなか、新たな裁判長・裁判官に対して原告と弁護団の意見陳述が行われました。
原告の宮西君代さんは「駅員さんがいなくなって予約が必要になり、当日の時間変更が難しく時刻に縛られる苦痛は当事者でないと理解できないのだろうか。公共交通機関であるべきJRが時代に逆行して、交通弱者を切り捨てている」と、裁判進行中にも無人化や窓口廃止を拡大するJR九州のあり方を批判しました。
森脇弁護士は「障がいを有する方々の『移動の権利』は、憲法によって保障された極めて重要な権利」と判例を踏まえて主張しました。
松尾弁護士は「JR九州は3877億円の税金と多くの優遇を受け、国会で『不採算部門を切り捨てない』『安全性を第一にする』と約束している。責任を持って約束を守るべき」と弁論しました。
報告会には60人を超える人が参加しました。
徳田弁護士は「多くの方が参加してくださったことで、この裁判が障がい者と身近にいる人たちにとってどんなに大事な裁判かを新たな裁判官に伝えることができた」と意義を話しました。
東京から参加した視覚障がい者の鷹林茂男さんは、「視覚障がい者は月に数人がホームから転落している」というデータを紹介し、命に関わる問題として東京でも駅無人化反対の取り組みを行っていることを伝えました。
入院治療中の吉田春美さんもラインで参加し報告を聞きました。
なおこの日、口頭弁論が始まる前に署名の第2次提出(5113筆)を行いました。
次回口頭弁論は9月29日16時から行われます。
JR駅無人化反対訴訟第6回口頭弁論(7月7日)の日程
コロナ感染のため制限されていた傍聴席も制限が解除される予定です。入廷行動で原告や弁護団とともに入廷し、原告と弁護団の意見陳述を傍聴し、報告会で裁判の状況と意義をみんなで共有しましょう!集合時間は13時20分、入廷行動は13時30分を予定しています。傍聴は事前に抽選が行われる可能性があります。
「JR駅の無人化に反対する市民集会」(3月5日)の報告
「人生の中で2度ホームから転落しました。いずれも駅員さんが私の命を救ってくれました。もし、あの時駅員さんがいなかったら、私は現在この世にいることはありません。駅員さんの存在は私達視覚障碍者の命をつなぐ、掛け替えのない存在です」という声。
「JRが大好きでほんとによく利用するが、帰ったときに『よかった。私は今日も無事だった』と思う。駅員さんがいてもそうなのに、いなくなったらどうなるでしょう」という盲導犬利用者の声。
「障害者や高齢者などの交通弱者が公共交通機関を安心して利用するためには、やはり人の支えが不可欠」と木村英子参議院議員からもメッセージが寄せられました。
地域の人からも「住民に説明をしないJR」への批判の声が出されました。
「駅で合理的配慮を行うためには駅員さんが必要」という声が広がっています。
裁判の報告では、「4000億近い税金を受け取り、年間100億円近い運用益を上げていて、赤字を理由に無人化を進め、さらに税金で負担してくれ」と自治体に求めてくるJR九州のあり方が批判され、「一人ひとりの住民のためのJR、住民のための駅を取り戻すためには、この裁判に勝つことが重要」というお話がありました。
参加者は、「これからも何度も集まってJR九州の姿勢を検証しJR九州に対して問題を指摘していく」ことを確認しました。
3月5日、「JR駅の無人化に反対する集会」を開催します
JR九州は昨年末の12月23日に「駅体制の見直し」を発表しました。九州全域で駅無人化を拡大し、販売窓口の閉鎖・時間短縮を進めるという内容です。
大分県内では、東別府・暘谷・大神・天ヶ瀬駅を無人化、別府大学・西大分・南大分駅で販売窓口廃止し、さらに多くの駅で販売窓口・改札時間を短縮するとしています。駅頭とインターネットで告知するだけという一方的な進め方です。
私たち県内16の障がい者団体は1月12日、JR九州に対して「①説明会を開くこと②住民や障がい者の意見を聞いて問題解決の努力をすること③納得を得るまで実施しないこと」を要請しました。
しかしJR九州は説明会の開催を拒否、私たちの声や思いはJR九州に届きませんでした。
私たちは黙っているわけにはいきません。
「告知」のみで一方的に実施することをこのまま認めてしまうと、今後、同じ手法でさらに多くの駅で無人化が進み、利用できない人、困る人が増えることになります。
地域で暮らす私たちにとって、JR九州は何よりも地域の公共交通の要です。
民営化の際に国鉄の資産を受け継ぎ、完全民営化の際には税金による基金3877億円を受け取っており、公共的な役割を果たさなければならない企業です。
駅無人化や販売窓口廃止の影響を受けるのは、障がい者だけでなく高齢者や学生など多くの地域の人たちです。
住民の安全、安心な生活を守る立場から、私たちは賛同団体の皆さんと一緒に「JR駅の無人化に反対する集会」を3月5日に開催します。
ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。
コロナ感染等に備えるため、オンライン参加の準備もします。
また、ファックスやメールによるメッセージやご意見もいただき、集会で共有したいと思います。
私たち一人ひとりの思いと行動が、これからのJRと公共交通のあり方に大きな影響を与えることになります。
可能な方法を選びながら、JR九州に対して、そして九州各地や全国に向けて最大限の意思表明を行っていきましょう!
①日時 3月5日(土)14時~16時
②会場 大分コンパルホール 3階 多目的ホール
オンライン(Zoom)参加ご希望の方はメールアドレス info@daremoga-oita.net までご連絡ください。
JR駅無人化反対訴訟第5回口頭弁論の報告
今回はJR九州が無人化駅拡大を発表したなかでの裁判となりました。
原告の吉田春美さんは自ら意見陳述に立ち、文字盤と代読で「JR九州は、駅無人化による不便と不安を訴える声に耳を貸さず、障がい者がわがままを言っているような構図をつくろうとしている」とJR九州の姿勢を批判し、無人化の拡大によって「もはや障がい者だけでなく、高齢者や女性や子ども、地域の足はJRしかない人たちみんなの問題になった」と裁判の意義を訴えました。
報告集会で徳田弁護士は、JR九州から出された反論について「『駅の無人化は赤字対策だ』という私たちの主張に正面から答える形になり、お互いの主張が正面からがっちりとかみ合ってきた」と述べました。
その上で徳田弁護士は、JR九州が「経営全体で年間400億円の莫大な利益を上げていたにもかかわらず、鉄道部門を切り離して20億円の赤字を理由に無人化を強行」しようとし、「数千億円の税金が投入されている公共交通機関であるにもかかわらず、赤字対策で人件費を節減するために無人化は仕方ないという論理」を主張していることを批判。今回の無人化拡大によって既成事実化を進め、被災地天ヶ瀬を始めとする利用者や地域に不便を強いるJR九州に対して、住民や自治体の問題として取り組みを広げていくことを呼びかけました。
報道機関や参加者との質疑では、裁判の意義について「私たちの監視の目がなくなれば、JR九州は最終的には豊かな路線しか残さないことになる」、JR九州が自治体による代替を提案していることについて「自治体の判断を尊重するが、地域としては限界があり、公共交通機関であるJRとして本来の対応ではない」などの意見が出されました。
参加者から「解決の方向性として地域の住民が介助する方向は考えられないか」という意見も出されましたが、吉田春美さんは「僕の場合はヘルパーさんであってもJR利用の介助は誰でもできるわけではない。駅の近所の人が僕を助けるのは難しい」と話しました。この意見交換で、障がいの種類や程度によって必要な支援が異なることが共有されました。
支援する会の平野共同代表は、「公共というのは不特定多数のいろんな人たちが使える場でなければいけないと私たちは考えている。吉田さんの大変さは、私たちは経験できない。だから吉田さんが教えてくれる。宮西さんらも教えてくれる。私たちはそれらを学びながら社会全体で考えていく。それが公共について考えることであり、裁判の意義であり、我々がめざすことだと思う」と指摘。
バリアフリーと合理的配慮についても、「バリアフリー法で全部基盤整備ができるわけではない。一人ひとりがいろんな事情を抱えている。それに対して対応するのが合理的配慮。駅員が一人いることによって合理的配慮がたくさんなされてきた。だから私たちの要求は合理的配慮の手段を奪うなということです」と裁判の意義を伝えました。
最後に 3月5日の「JR駅の無人化に反対する集会」について、「一人でも多くの人が参加してみんなの考えが自由に述べられるような場になれば」という願いが伝えられ終了しました。
裁判と駅無人化反対の取り組みの意義がますます明確になってきています。
集会への参加と周囲の人たちへの広報、自治体への呼びかけ等をみんなで進め、みんなのための公共交通を守りたいと思います。
JR駅無人化反対訴訟第5回口頭弁論の日程
新型コロナ感染拡大のため、入廷行動は行いません。
2022(令和4)年2月10日(木)
14時10分 一般傍聴整理券配布(車椅子傍聴席をご希望の方はつくる会までご連絡ください)
14時15分 参加者集合
15時 第5回口頭弁論
15時50分 報告集会(会場 大分県弁護士会館)
傍聴及び報告会にご参加ください。
JR駅無人化反対訴訟を支援する会のホームページでもご案内しています。支援ニュース(1-4号)等もダウンロードできます。
JR駅無人化反対訴訟支援ニュース第4号(11月30日)発行
JR駅無人化反対訴訟を支援する会ホームページ でダウンロード(PDF)できます。(バックナンバーもダウンロードできます。)
「障がいのある者特に重度の障がいのある者にとって、公共交通機関を利用することは、単なる移動の手段だけでなく、自立と社会参加を意味する」という考え方にもとづいた主張が展開されています。
JR駅無人化反対訴訟第4回口頭弁論の日程
11月11日(木)
13時45分 大分地裁前集合
13時55分 入廷行動
14時(予定)傍聴整理券配布
15時 第4回口頭弁論
終了後、報告会(会場 大分県弁護士会館)を行います。
ぜひ入廷行動、傍聴、報告会へご参加ください。
JR駅無人化反対訴訟第4回口頭弁論は11月11日(2021年)
駅無人化反対訴訟を支援する署名を継続中です。 署名用紙はこちら 、 チラシはこちら からダウンロードできます。
また、支援する会への入会やご寄付も歓迎します。 入会申込用紙をこちらからダウンロード(PDF)できます。
JR駅無人化反対訴訟支援ニュース第3号(9月30日)発行
JR駅無人化反対訴訟第3回口頭弁論の報告
「移動する権利」は憲法13条の幸福追求権と22条の居住・移転の自由を根拠として保障されています。それは「仕事などの経済活動だけでなく、交流や見聞を広めたり、人生を楽しんだりする上で無くてはならない権利」です。
しかし、障がいがある人にとっては、「障がいによって受ける制約(障壁)が取り除かれない限り、移動の権利』が保障されたとは言え」ません。原告のように重い障がいがある人にとっては、「JR等の公共交通機関を利用することは、単なる移動手段ではなく、利用すること自体が、喜びや達成感を感じたり、人と交流したり、自分らしく生きる手段として、極めて重要なもの」です。
このように大切な「移動の権利」が、駅を無人化したことで侵害されました。また、事前の予約や調整なしに利用できなくなったこと、予定通りに行動できなければ利用できない状態は、「移動の権利」が保障されていると言えません。
意見陳述は、以上のような主張を明確にした上で、「社会全体が、我がこととして受けとめ」、「障がいを有する人々に、我慢や負担を強いるのではなく、『合理的配慮』の提供によって、障壁を取り除くという視点をもって、この裁判が進められていくことを、切に願っています」と締めくくられました。
私たちは、「障がいがある人の移動の権利は、憲法に定められた重要な権利」という主張を「我がこと」として高く掲げてこれからの取り組みを進めたいと考えています。
これからの裁判では、より具体的に原告の利用時の状況やSSS(スマートサポートステーション)の対応や体制など、具体的な検証も重要になってきます。
みんなで裁判を支援し、障がいのある人の移動の権利の主張がしっかりと受けとめられ、裁判を通して社会の共通理解になっていくように取り組みを広げていきましょう。 (文責・事務局)
JR駅無人化反対訴訟第2回口頭弁論の報告
引き続いて3名の原告と弁護団、支援する会の代表が、皆さんから寄せていただいた39,536筆の署名を大分地方裁判所に提出しました。
署名は大分県内の個人、様々な団体、そして全国の障がいのある人や団体から寄せていただいたものです。署名は今後も、一人ひとりに声かけをし、理解を広げ、みんなの声を伝えるために継続して取り組みます。
口頭弁論で宮西君代さんは、「これまで思い立って駅に行きさえすれば駅員さんに手伝ってもらって普通に乗れたのが、前日の夕方までの電話予約が必要になった。一人で電話ができない、聞き取りが困難な私の場合、人に頼まなければならない苦痛や時刻に縛られる苦痛はとても大きい。私たちは、公共交通機関を利用して、街に出て行き、私たちの存在を知ってもらい、理解し合い、市民みんなでやさしいまちづくりを進めてきた。気軽に街に出て行く権利をうばい、社会参加を著しく制限し、共生社会の後退につながる駅の無人化に断固反対します」と述べました。
続いて意見陳述を行った松尾弁護士は、「JR九州は『一民間企業であり、法的には障がい者に対する合理的配慮の責任を負わない』と反論している。しかし、JR九州は単なる一民間企業ではない。JR九州は株式上場時に、税金で設けられた3877億円の経営安定基金を資産に組み込んだ。その際に青柳社長は国会で『九州の鉄道ネットワークの維持は当社にとって重要な役割』『今後とも安全を最優先にした経営に努める』と答弁している。赤字が見込まれる鉄道事業を維持するための基金をもらって、赤字になりそうだから無人化させてくださいというのはおかしい」などと指摘しました。
報告会では、徳田弁護士が、「宮西さんは全身を振り絞って思いを伝えた。吉田さんと宮西さんの意見陳述を裁判所や多くの人たちに聞いてもらえて、最初の山を越えたと感じる」と述べました。
第2回口頭弁論の詳しい報告は、駅無人化反対訴訟を支援する会の ニュース第2号(PDF)でご覧になれます。
JR駅無人化反対訴訟第1回口頭弁論の報告
当日の意見陳述や報告会について報告します。
またこの日は「JR駅無人化反対訴訟を支援する会」の結成も行われましたので合わせてご報告します。
以下、報告です。
○意見陳述
原告の吉田春美さんが、「電車に乗って移動することが大好きだが、無人化によって事前の予約が必要になり、当日の時間変更や駅の変更ができない。今後もJRに乗って社会参加を続けたいので、高城、鶴崎、大在、坂ノ市、中判田、5駅の無人化の白紙撤回を求める」と意見を述べました。
代理人の平松まゆき弁護士も、「JR九州は極めて高い公共性を有する。事前の予約や調整なしに利用できなくなった車いす利用者の権利利益の侵害は、JR九州が被る負担より深刻である。当事者の声に謙虚に耳を傾け、誰もが安心して暮らせる社会を共に作るため、自らが何をなすべきかがこの裁判で問われている」と意見陳述を行いました。
○報告会
徳田弁護士が、この裁判の意義について、「障がい当事者が裁判を活用し、裁判の場で主人公として行動するという、日本の裁判史上極めて意義のある1日だった」と述べました。
平松弁護士は、車いすや盲導犬を利用する人たちの裁判参加に向けて裁判所と協議を行ったことを紹介し、「気づかされることが多かった。そのことを通して学ぶことができる。気づきを自分のものとしながら取り組みたい」と話しました。
原告の吉田春美さんは、「とても楽しかった。文字盤で意見陳述したのは全国でも僕が初めてだと思う。これからも文字盤を使って楽しい裁判にしたい」と文字盤で感想を述べました。
宮西君代さんは、「言葉に障がいがあって予約が困難でも、一人でJR駅を利用して自由をたのしみたい。裁判では、聞き取りづらい言葉でも、自分の言葉で訴えたい」と話しました。
五反田法行さんは、車いす傍聴席が4席しかなく入れない人がいたことについて、「難しいかも知れないが、傍聴希望者が多いので、もっと多くの人や車いすの大きさにも対応してもらいたい」と指摘しました。
徳田弁護士は、争点について、記者からの質問に答えて、「駅無人化が車いす、盲導犬を利用する人にとって差別になるか、合理的配慮を欠いているか」という点と「障害者差別解消法は民間企業については努力義務としているが、公共交通機関であるJR九州についてどう解釈するか」という点を挙げ、「JR九州は極めて公益性が強い企業であり、九州の人の足を守るために巨額の税金が投入されている」ことを指摘しました。今後の展開については「無人化の不利益について具体的な主張を行っていくことになる。実際に車いすや盲導犬利用者の駅利用や予約調整の検証を行いたい」と話しました。
○JR駅無人化反対訴訟を支援する会 結成会
報告会のあと、「JR駅無人化反対訴訟を支援する会」が結成されました。
結成の趣旨として、「①JR駅無人化反対訴訟を支援②JR九州に対して、だれもが利用しやすい公共交通としての役割を果たすよう求める③障がいに対する理解を深め、障がいがあってもなくても、安心して暮らせる地域づくりをめざす④障がいのある人もない人もだれもが参加できる市民の会として、裁判の傍聴や支援、署名など、それぞれ自分にできることに取り組む」という4つを全員の拍手で確認しました。
会則として「会の目的に賛同するものは個人団体を問わず誰でも参加できる」ことなどが確認され、共同代表に平野亙さんと志賀等さん、事務局長に阿南静生さんが選出されました。
JR駅無人化反対訴訟弁護団の徳田弁護士は「私たちの裁判として、溢れかえる人たちの雰囲気のなかでやっていきたい。裁判所もそれを受けとめる。長いたたかいになるが“楽しみながら”心を一つにして取り組みましょう」と今後の取り組みを呼びかけました。
今後の裁判支援の取り組みについては、「JR駅無人化反対訴訟を支援する会」が中心になっていきますが、つくる会も引き継ぎを行い協力しながら継続して取り組むことになりますので、皆様のご支援ご協力を心からお願いいたします。
みんなで力を合わせて、裁判の場で障がいがある人たちの移動の権利を勝ち取りましょう!
駅無人化反対訴訟を支援する会の ニュース第1号をこちらからダウンロード(PDF)できます。
JR駅無人化反対訴訟支援へ署名活動を開始
まず、署名用紙とチラシをお届けします。できるだけ広く(県外も含めて)配布して協力を呼びかけていただければと思います。印刷したものが必要な場合には必要数を事務局までご連絡ください。
期限は設けていません。裁判の進行に合わせて、集まったものから届けていきたいと考えています。
次に、2月4日の第1回口頭弁論の傍聴と支援する会結成会への参加と呼びかけをお願いいたします。
傍聴席の数は流動的で抽選になる可能性もありますが、終了後の報告会で原告や弁護団の皆さんから詳しい報告が行われますので、できるだけ多くの方にご参加いただきたいと思います。車いす席は4席に限定されていますので、傍聴を希望される場合は介助者の有無を含めて早めにご連絡をお願いします。
またこの日は「JR駅無人化訴訟を支援する会」を結成します。まわりの方にも広く参加を呼びかけていただきたいと思います。
・第1回口頭弁論 2月4日(木)15時30分 大分地方裁判所
・報告会・「JR駅無人化訴訟を支援する会」結成会
2月4日、第1回口頭弁論終了後引き続いて開催 大分県弁護士会館(大分市中島町)
みんなで力を合わせて、裁判の場で障がいがある人たちの移動の権利を勝ち取りましょう!
駅無人化反対訴訟を支援する 署名用紙をこちら からダウンロード(PDF)できます。
2020年の取り組みの報告
残念ながら、新型コロナウィルスの感染拡大は多人数の会議や行動を困難にしましたが、そのなかで可能な方法を模索しながら、いくつかの取り組みを実現することができました。
JR駅の無人化については9月23日、JR九州を相手に裁判を起こしました。
車いすを使用する吉田春美さん、宮西君代さん、五反田法行さんの3名が原告になり、徳田靖之弁護士を始め県内の11名の弁護士さんたちが弁護団を結成しました。
提訴は全国的に大きく報道され、他県の障がい者団体からも共感の連絡をいただくなど、だれもが安心して利用できる公共交通をみんなで考える大切な場になっています。
年が明けて2021年2月4日(木)には第1回口頭弁論が大分地方裁判所で15時30分から開かれます。終了後には引き続き報告会と「JR駅無人化反対訴訟を支援する会」の結成会を開催しますので、ぜひご参加ください。
旧優生保護法に基づく優生手術(強制不妊手術)については、大分県で746人が被害を受けたことが明らかになっていますが、救済は遅れています。
法律による一時金支給を受けた人は県内で30人にとどまり、名簿が残っている101人の方は一人も含まれていません。
県と意見交換を重ね積極的な対応を求めています。
地域では、福祉フォーラムや相模原事件を考えるシンポジウム等の開催は困難な状況でしたが、国東市では精神障がい者国東フォーラムが規模を縮小してスタディ・ミーティングとして12月3日に開催されました。
講師もビデオを活用し、座席の間隔を広く取って行いましたが、議員等の参加もあり継続の重要性を感じさせる行事となりました。
この他にも、施設入所利用の調整問題、大林さんから提起をいただいた「終活」の課題、災害時における医療的ケア児・者の電源確保など、つくる会に寄せられた様々な問題に力を合わせながら取り組んで参りました。
再開したつくる会の会議も、最近のコロナ感染再拡大の状況の下で次回がまだ決まっていませんが、2月4日にはJR駅無人化反対訴訟の第1回口頭弁論、報告会、訴訟を支援する会の結成会が行われます。
感染対策を講じながらぜひご参加いただきますよう重ねてお願いいたします。
来年もまた皆様と一緒に、よりよい地域をつくっていくために力を合わせて進んでいくことができればと願っています。
2019年の取り組みの報告
1月には「大分県障がい者計画(素案)」に意見を提出。3月には大分県議会で行われた「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる県づくり特別委員会」の報告を受けて、県(障害福祉課、障害者社会参加推進室、福祉保健企画課、健康づくり支援課、こども未来課)と意見交換の場を持ちました。つくる会から「条例の県民への浸透、行政への浸透は不十分」だとして、「書かれたことの具体化が重要」とした上で、条例の周知、「性・恋愛・結婚・出産・子育て」「防災」「親なきあと」の取り組みの具体化等について積極的な取り組みを求めました。
2017年から取り組んでいるJR駅の無人化については、「障がい者に対する合理的配慮を欠くもの」として、条例にもとづいて県に対して特定相談を申し立てました。しかし県の対応では解決の見通しがつかなかったため、JR九州を相手に裁判を起こすことを決定しました。
旧優生保護法に基づく優生手術(強制不妊手術)については、大分県で746人が被害を受けたことが明らかになっていますが、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の成立にもかかわらず救済が進んでいません(現時点で認定されたのは11人)。このため県と意見交換を重ね、積極的な対応を求めています。
地域では、3月に日田市で「日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例」が成立、7月に「第3回相模原事件を考えるシンポジウム」(中津市)を開催、11月には佐伯市で「福祉フォーラムinけんなん佐伯会場」が開かれました。また別府市では市条例にもとづいて、障がい者と地域が一緒に取り組むインクルーシブ防災や障がい者が講師になる学校訪問ワークショップ事業などの取り組みが継続されています。
「第3回相模原事件を考えるシンポジウム」では、障がいがある人への支援の役割が家族に集中している現実、地域の人が知ることで暮らしやすくなる可能性などが話し合われるとともに、「役に立たない」「生きる価値がない」など優生思想につながる根深い差別意識が今も存在し続け、克服できていない課題があることが明らかにされました。
「福祉フォーラムinけんなん佐伯会場」では、障がいのある人と家族10人から「点字ブロックが途中で切れているところがある」(視覚障がい)「病院などで名前を呼ばれても聞こえずずっと待っている」(聴覚障がい)「一般就労しているが理解が広がらない」(発達障がい)「ヘルパーが足りない」(身体障がい)「親なきあとを支えてくれる福祉サービスを」(家族)「子どもが災害時に避難先で一緒にいることができない」(家族)など多くの声が出されました。
この他にも、参議院選挙への投票ができなかった問題、病院からの外出への様々な制約、発達障がいの人の就労支援が不十分であること、重度障がい者の就労において重度訪問介護を利用できないこと、支援事業所のあり方など、つくる会に寄せられた様々な問題に力を合わせながら取り組んで参りました。
来年も様々な課題が出てくることと思いますが、皆様と力を合わせながら一つずつ取り組んでいければと願っています。 新たな年もどうぞよろしくお願いいたします。
9月に発行した「第3回相模原事件を考えるシンポジウム」の報告集を こちらでご覧(ダウンロード)いただけます。
2019年5月11日(土)、つくる会総会とシンポジウム開催
「障害者差別解消法」の施行からも3年になります。
この3年間、つくる会はさまざまな取り組みをしてきました。条例を県民に知ってもらうためのパレード、相模原事件を考えるシンポジウム、いのちの重さを考えるシンポジウム、JR駅の無人化に反対するる取り組み、選挙の投票を保障する取り組み、さまざまな相談、県との意見交換 等々。
2019(令和1)年5月11日(土)、県条例と差別解消法の施行によって何が実現し、何ができていないのかを皆さんと一緒に考え、安心して暮らせる地域づくりをさらに進めていきたいと考えます。
つくる会の総会は5月11日の午前10時から大分市のホルトホール大分3階302・303会議室で行います。
内容は、
①条例の3年間の成果と展望(平野亙・共同代表)
②JR問題、投票保障の問題について(徳田靖之・共同代表)
③別府市におけるインクルーシブ防災の取り組み(湯澤純一・共同代表)
です。
ぜひ、ご出席ください。
また同日、同じ会場で12時30分から「障害者差別解消法・障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例施行3周年を考えるシンポジウム」が開かれます。
「NPO法人自立支援センターおおいた」の呼びかけでつくられた実行委員会の主催で、ヒューマンネットワーク熊本の植田洋平事務局次長が講演し、県内の障がいのある人、家族、支援者等による意見発表やシンポジウムが行われます。
合わせてご参加いただけましたら幸いです。(チラシはこちらからダウンロード できます)
なお、総会終了後、シンポジウムの開会前の時間(11時15分頃~12時頃)には障害者差別解消法と大分県条例を知らせるためのチラシ配布行動も予定されています。可能な方はご参加いただきますようお願い申し上げます。
10月16日、JR駅無人化反対署名73113筆をJR九州に提出
JR大分支社長の回答は「7万人の署名の重さは受け止める」としながらも、「大分大学前駅と敷戸駅については準備が整い次第進める」と答え、残る5駅については「エレベーターの設置などバリアフリー対策を進めて実施する」と無人化実施の姿勢を変えませんでした。
また、減便についても「イベントや学校のテストなど個別に対応している」として減便の見直しは行わない考えを示しました。
これに対してだれもが安心して暮らせる大分県をつくる会の徳田靖之共同代表は、「JR九州が無人化の姿勢を全く変えず、話し合いもしないのであれば、障害者差別解消法や大分県条例を使ってJRと全面対決するしかない」とJRに伝えました。
参加者からは、「線路から転落した場合、監視カメラでは対応が間に合わない」「元々乗れない駅について問題なかったというのはおかしい」「駅員さんがいなくなると乗れなくなる。事前に連絡すれば対応するというのは差別だ」など切実な意見が出されました。
これに対しても、「SSS(スマートサポートステーション)の導入で今まで以上に安全になると考えている」というこれまでの回答を繰り返し、あくまでも無人化推進の姿勢を変えませんでした。
昨日(10月17日)に記者会見を行った青柳社長は「『署名の重みを考えると、これまで以上に障害のある方の声を聞いていく必要がある』と発言。必要があれば説明し、対策をとる考えを示した」(10月18日・大分合同新聞)と報道されています。
しかし「説明」は実施に理解を求めるため繰り返しにすぎず、「対策」は個別事例への逐一の対応にすぎないというのが現実です。障がいについて、これまで配慮が十分ではなかったという指摘を受け止めて、どうすれば利用しやすくなるのかを障がいのある人たちと一緒に話し合うことこそ、JRがまず行うことではないでしょうか。
この行動は、これからの公共交通のあり方を左右する重要な意味を持っています。
JRが海外の大株主のために地域住民を切り捨てることがないよう、声を上げ続けていくことが大きな意味を持っていると考えます。
「JR駅の無人化反対署名」7万人を超える!!」―2度目の反対集会を開催
以下、呼びかけ文を転載します。
「JR駅の無人化に反対する署名」は、目標を大きく上回り7万人を超えました。
このことは、JR駅の無人化と減便に対する皆様の強い反対の声を示すとともに、地域の公共交通の担い手としての役割を放棄しつつあるJR九州に対する強い警鐘であると考えます。
ところが、JR九州の青柳社長は2018年8月27日の記者会見で、「(自治体負担の)話が進まないようであれば、『鉄道維持は難しい』と地元の皆さんがおっしゃったという認識になる」と発言し、その後大分・福岡両県と日田市などから「緊急要請」を受けて担当本部長が謝罪したと報じられています。
同社長は7月にも、「輸送密度(1キロメートル当たりの1日の利用人数)が2000―4000人未満のところは、鉄道維持が非常に困難。将来的に地元との協議が必要になる」と発言しており、公共交通としての鉄道維持に後ろ向きの経営者であると言わざるを得ません。
JR九州は、国有財産を受け継いで、駅や駅周辺等の不動産を活用した事業によって大きな利益を上げています。
さらに、国(税金)から経営安定基金(3,877億円)の支援を受けている企業です。
経営努力は評価しますが、不採算路線や駅員さんたちを切り捨てることによって、外国資本等の株主への配当を増やすことは筋違いと言わざるを得ません。 私たちが求めていることは過大なことではないはずです。
「駅に駅員さんを残してください」
「通学や通院の時間帯に2時間も空白時間を作るような減便をやめてください」
「いろんな立場の住民と開かれた意見交換をするとともに、意見を反映してください」
このような声を受け入れようとしないJR九州に対して、私たちは声を上げ続けたいと思います。
そのために9月24日、「JR駅の無人化に反対する集会」を開催いたします。
ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。
1,日時 2018年9月24日(月・休)14時
2,場所 大分市 コンパルホール 4階 400会議室
3.内容
署名結果の報告と様々な立場の人の意見発表を行い、今後の取り組みの方針について話し合います。
主催 だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会
共催 大分県障がいフォーラム・障害者の生活と権利を守る大分県連絡協議会
連絡先 大分市都町2丁目7-4-4-303 在宅障害者支援ネットワーク 電話097-513-2313 FAX097-529-7212
「JR駅の無人化は障がい者への差別!!」―反対する署名を開始しました
障がいのある人からは、「駅員さんがいなくなると安心して乗れなくなる」「予約をしないと乗れないのは差別」、地域の人は「高齢者が利用しにくくなる」「地域がさびれる」等と強い反対の声が上がっています。しかしJR九州は、一部を延期したものの、無人化と減便を進める姿勢をまったく変えていません。また、「スマートサポートステーション(S.S.S.)の導入により、駅員がいる現状より安全になる」などと説明していますが、一人が10駅のテレビカメラを監視して係員を派遣するというのですから間に合わないことが多くなるでしょう。とても責任ある対応とは言えません。
驚くことに、県内JR85駅中55駅が既に無人化されています。このまま見過ごしてしまうと、大分市だけでなく大分県内全域に無人化や廃駅が進み、それは九州全域にも及ぶことになります。地域の交通を守るためには、残された数少ない有人駅である大分市内の駅無人化を食い止めなければなりません。
JR(日本旅客鉄道)はもともと国有鉄道(国鉄)でした。国の財産を受け継いで、駅に商業施設をつくり、様々な事業を運営することによってJRは利益を上げています。公共交通である鉄道を「赤字」を理由に切り捨てていくことはできない立場の企業であるはずです。私たちは、公共性を失いかけているJR九州に対して、しっかり声を上げたいと思います。
このため、障がいのある人や地域の人たちの声を広く多く集めるための署名活動を開始することにしました。署名活動を通して、JR九州に対して以下のことを求めます。
皆様のご協力をお願いいたします。
1,駅の無人化の方針を撤回すること。
2,減便の方針を見直すとともに、新たな減便等については地元自治体・議会・自治会・住民の了解なしに行わないこと。
3,障がい者をはじめ様々な住民のJR九州に対する意見を受けとめ、誠実に回答し、意見交換の場を設けること。
署名活動は8月末日(2018年)まで行います。
呼びかけ文と署名用紙はこちらからダウンロードできます。
「JR駅無人化に反対する署名の呼びかけ文」(PDF版)
「JR駅無人化に反対する署名用紙」(PDF版)
第2回 相模原事件を考えるシンポジウム~みんなで話そう~を開催しました
今回のテーマは「みんなで話そう」です。
第1回シンポジウムで十分に出せなかった方にも話していただけるように、できるだけ多くの人に思いを語っていただきました。
報告はつくる会の会報「わたしも あなたも」20号に掲載しています。
○第2回相模原事件を考えるシンポジウム「みんなで話そう」
日時 2018年1月28日(日)13時30分~16時
場所 大分県総合社会福祉会館 4階 大ホール
大分市大津町 2丁目1番41号
・入場無料
・手話・要約筆記を行います。
・駐車場には限りがありますのでできるだけ乗り合わせでお出でください。
主催 だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会・大分県障がいフォラーム実行委員会
事務局 在宅障害者支援ネットワーク
「相模原事件を考えるシンポジウム」を開催しました
犯人は、元施設職員でした。なぜ?そういう思想に至ってしまったのか?
「精神を病んだ若者が起こしてしまった事件」と決めつけてはいけない、もっと複雑でたくさんの問題があり、整理して考えていく必要性があると思います。
『最重度の障がいを持つ方も地域の中で安心して生きていける社会』を願って、みなさんと一緒に考えていきたいと開催しました。
報告はつくる会の会報「わたしも あなたも」19号に掲載しています。
○相模原事件を考えるシンポジウム 〜あの事件から1年 私たちは、どう受け止めたのか?~
・日時 7 月29 日(土)13 時30 分〜16 時
・場所 大分市ホルトホール(大分駅南側) 3 階 302・303 会議室
・内容
①事件の説明 廣野俊輔 氏
②—当事者としてどう受け止めたのか?
宮西君代 氏 重度脳性マヒ者の存在と地域との関わりについて
湯沢純一 氏 視覚障がいを持つ立場で
大林正孝 氏 入所者の立場から
③パネルディスカッション
コーディネーター 平野 亙 氏
パネラー 徳田靖之 氏
寄村仁子 氏
宮西君代 氏
阿部哲三 氏
主催 だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会・大分県障がいフォラーム実行委員会
「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」第6回総会を開催しました
「だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会」改め「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」は6月17日に第6回総会を開催しました。 条例が施行されて以降一年間余りの経過を振り返りながら、条例を「絵に描いた餅」にしないためにこれから何が大切なのかを一緒に考えました。
今回の総会では、地域の取り組みとして別府市における「災害時要援護者の防災」「親亡き後等の問題解決検討委員会報告以降の取り組み」の報告、けんなんフォーラム(佐伯)作成された大分県条例を知るためのビデオ「まっちとめぐちゃんのティータイム」上映を行い、障がいがある方やご家族の生活の現状や条例の活用のあり方などについて参加者みんなで意見交換しながら今後の取り組みについて話し合いました。
報告はつくる会の会報「わたしも あなたも」19号に掲載しています。
「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」第6回総会
日時 2017年6月17日(土)13時30分~16時
場所 大分市 大分コンパルホール 3階 300会議室
内容
・条例施行後の取り組み
・報告1「災害時要援護者の防災」(当事者参加訓練ビデオ上映)村野淳子さん(別府市防災危機管理課)
・報告2「親亡き後等の問題解決検討委-報告以降の取り組み」平野亙さん(大分県立看護科学大学)
・ビデオ上映「まっちとめぐちゃんのティータイム」
(福祉フォーラムinけんなん(佐伯会場)が作成した大分県条例を知るためのビデオ)
・意見交換 コーディネーター 徳田靖之さん(弁護士)
だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会
共同代表 阿部実・徳田靖之・平野亙・宮西君代・湯澤純一・寄村仁子
11月27日、「親なきあとを考えるフォーラム」を開催
平野共同代表が別府市の「親亡き後等の問題解決策検討委員会」の検討結果について報告し、「親なきあとマニュアル」に寄せられた思いなどについて報告を受けた後、当事者、家族、支援者、行政など様々な立場から思いや課題、取り組みなどを話し合いました。
当事者として参加した河野龍児さんは「4月の地震の際に親なきあとの問題を実感した。まわりの人の理解が大切だが、地域の理解はまだないと感じる。親が託せる、心のこもった“仕組みづくり”が必要」と話しました。
親として参加した永松温子さんからは「多くの親が4月の地震の際に『もういいや』『しようがない』と思ったという声を多く聞いた。親が抱え込んでいることが多い。親自身の人生も考えることが必要」と話しました。
別府市の大野福祉保健部長は「100人いれば100通りの解決策が必要」と対策の難しさを指摘した上で、「将来の問題ではないので早急に考えなければならない。緊急の問題から取り組み始めている。成功事例などを伝えていくことも必要」と話しました。
親であり支援者でもある安部綾子さんは「地域の理解、行政の理解が必要。制度があっても知らない人もいる。『どうしていいかわからない』という悲鳴に似た電話に、こちらも一緒に途方にくれる思いになることがある」と話しました。
この他にも重要な発言が多くあり、多くの課題が明らかになったフォーラムでした。詳しい報告は、つくる会の ニュースレター「わたしも あなたも」18号に掲載しています。
7月24日に「大分県条例お知らせパレード」を行いました!!
お一人おひとりの皆さんによる声かけ、川野陽子さんが立ち上げたフェイスブックによる呼びかけ、マスコミ報道、県議会議員の皆さんや行政関係の皆さんの参加などによって、想定を遙かに超えた規模になりました。
集会では、主催のだれもが安心して暮らせる大分県をつくる会共同代表・大分障がいフォーラム実行委員長の宮西君代さんがあいさつ。県議会議員から土居議員、県障害福祉課から高橋課長があいさつしました。
「条例を生かすために」をテーマに講演した徳田共同代表は「条例を絵に描いた餅にしないことが求められている。だれもが安心して暮らせる心豊かな大分県をつくっていくためには、あとは県に任せるのでなく、私たち一人ひとりが努力していくことが必要だ」と一緒に行動していくことを呼びかけました。
盲導犬と一緒に参加した湯澤純一共同代表は、障がいのある人の立場から、条例に対する思いを話しました。
パレードは、大分駅北口からセントポルタ中央町を通り、ガレリア竹町まで行いました。集会参加者の列に途中から合流する人もあり、行進は大きく広がりました。
みんなの力で、横断幕、チラシ、ティッシュ、掲示用カードなどを準備し、通行中の人や商店街の人たちに条例ができたこと、安心して暮らせる地域をつくるためにはみんなの力が必要なことを訴えました。
ガレリア竹町のドーム広場で閉会集会を開き、平野亙共同代表があいさつ。参加者約10人が感想を述べ、川野陽子さんの感謝と今後の協力を呼びかける言葉で閉会しました。
通行中の人だけでなく、新聞やテレビの取材によって、報道を通して条例について知ってもらうこともできたと感じています。
チラシ(3種、PDFルビ付・PDFルビなし・テキスト版)をご覧下さい。
「大分県条例を知らせるパレード」チラシ(ルビ付き)(PDF版)
「大分県条例を知らせるパレード」チラシ(ルビなし)(PDF版)
「大分県条例を知らせるパレード」チラシ(テキスト版)
「だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会」第5回総会の報告
リレートークでは約20人が発言。「できてよかった」「本当にうれしい」「できたあとが大切」「「県民に知ってもらいたい」「子どもたちに伝えたい」「学校の先生にも知ってもらいたい」「車いすでデートができるよう道をよくしたい」「この街に生まれたことを不幸と思わないように、どこに生まれても同じサービスを受けられるように」「別府市条例は取り組みが進んできている」「私の市でも条例をつくりたい」など、多くの思いが語られました。また「多くの人に知ってもらうためにパレードをしよう」という具体的な呼びかけもありました。
方針の提案は徳田共同代表が行いました。
「みんなでつくったこの条例を誇りにしたい。“生の声”を聴くことで生きる重みを実感し、私たち一人ひとりが成長した。これからどうしていくか。共通するのは『絵に描いた餅にしない』ということ。私たちに何ができるか。『親なきあと』『性・恋愛・結婚・出産・子育て』『防災』について対策を検討する機関が必要だ。条例によってできた『差別解消・権利擁護推進センター』を活用することも大切だ。そして地域の取り組みを進めるためには全市に条例をつくることが必要だ。知らせるためのパレードにも取り組みたい」と提案。また「条例をつくる会」について、名称を「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」に変更して活動を続けていくことを提案し、「全市」を「全市町村」に修正した上で、すべての提案が全参加者の賛同により承認されました。
総会の詳しい内容はニュースレター「わたしも あなたも」第17号(4月末発行予定)で報告します。
今後は「だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会」として活動していくことになりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
※大分合同新聞が4月11日から、「自分らしく-県条例と共に」(朝刊・5回続き)を掲載しています。
「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」については、大分県ホームページ(障害福祉課「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」についてのページ)でご覧いただけます。
「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」が成立
条例をつくる会から約20名が傍聴して成立を見届けました。成立後、県政記者室で記者会見を行うとともに、田中県議会議長、紹介議員になってくださった土居県議や守永県議をはじめとする県議の皆さん、草野福祉保健部長らにお礼の気持ちを伝えました。
条例をつくる会は、3月30日に世話人会、4月10日に総会を開いて、条例の成立について報告するとともに、これからの会のあり方や今後の取り組みなどについて話し合うことにしています。
みんなの声でつくった条例をこれからどう活かしていくのか、みんなで話し合っていきたいと考えています。
ぜひご出席をお願いいたします。
○世話人会
日時 3月30日(水)18時30分
場所 大分コンパルホール 3階 302会議室
○だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会第5回総会
日時 4月10日(日)14時
場所 大分県総合社会福祉会館 4階大ホール
だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会
共同代表 阿部 実・徳田靖之・平野 亙
宮西君代・湯澤純一・寄村仁子
平成28年第1回大分県議会に条例案が上程されました
条例をつくる会は、3月1日に事務局会議を開いて条例案の検討を行います。また、3月30日には世話人会、4月10日には総会を開いて今後の取り組みについて話し合う予定です。
県議会の日程は、一般質問が3月7・8・9日、常任委員会が3月17・18日に行われ、3月25日閉会の予定です。
条例案については3月18日に委員会で審議・採決が行われ、3月25日の本会議で議決される予定です。
県議会に上程された条例案です。
≫障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例案(word版)
ニュースレター「わたしもあなたも」最新号(第16号)を掲載しました
パブ・コメに129件の意見-第1回定例会上程・4月1日施行に向け一歩一歩
パブリックコメントの寄せられた主な意見は、「差別の禁止だけでなく差別が生じないように啓発・研修の充実が必要」「前文に障がいのある人やその家族の思いが入れられており感銘を受けた」「紛争解決機関の役割に権利擁護推進の取り組みを追加してほしい」などで、これらの意見を参考にしながら条例案の修正を行うとのことです。
さらに、来年(2016年)1~2月に条例施行規則の制定準備(パブリックコメント実施)を行い、2~3月に開かれる予定の第1回定例県議会で条例案の上程と施行規則及び関連予算案の提案を行い、可決されたら4月1日に施行する予定であることを明らかにしました。
また障がい者差別解消法も4月1日に施行されることから、2月21日には「障がい者差別解消フォーラム」を開催して差別解消法と条例案について理解を深めていくとのことでした。
「条例案」パブリックコメントが実施中です
条例案や意見応募の方法等は 大分県ホームページ(県民意見募集中)でご覧いただけます。ぜひご覧いただき、皆様のご意見を積極的にご提出いただければと思います。
条例案や意見応募用紙なども大分県ホームページ(県民意見募集中)からダウンロードできます。
また、以下の場所で見ることができようになっています。
ア 福祉保健部障害福祉課(県庁舎別館1F)
イ 大分県情報センター(県庁舎本館1F)
ウ 地区情報コーナー(下記事務所内)
・東部振興局・南部振興局・豊肥振興局・西部振興局・北部振興局
・豊後高田土木事務所・別府土木事務所・臼杵土木事務所
・豊後大野土木事務所・玖珠土木事務所・中津土木事務所
条例をつくる会臨時総会を11月1日に開催
日時 11月1日(日)13時30分から
場所 大分市中央町4丁目2番5号 ソレイユ 7階 カトレアA
○パブリックコメが始まりました(10月21日~11月20日)
10月21日、パブリックコメントが開始されました。
条例案の名称は「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例(案)」で、条例案や意見応募の方法等は 大分県ホームページ(県民意見募集中)でご覧いただけます。
12月県議会で県が条例案を上程へ
だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会「第4回総会」のご案内
昨年(2014年)3月の県議会の請願採択を受けて条例づくりに取り組んできた大分県は、今年(2015年)2月の第2回条例検討協議会で県としての「条例素案」を提案しました。これに対して障がい者団体や経営、交通、医療、教育、放送など各分野を代表する委員による議論が行われています。私たち条例をつくる会としても、世話人会や事務局会議で話し合いを重ねながら、県の「条例素案」に対する声をまとめ、「修正案」を提案しています。
今回の総会では、この1年間の取り組みを報告するとともに、県の「条例素案」と条例をつくる会の「修正案」について皆様に説明してご意見をいただきたいと考えています。同時に、昨年4月に「障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例(ともに生きる条例)」を施行した別府市の取り組みについて、行政の担当者及び協働を進める市民(障がいがある人)にお話ししていただきます。
「なぜ条例をつくるのか」「条例をつくることで何ができるのか」「県民・市民の役割は」-いろんな立場から、安心して暮らせる地域づくりのあり方を話し合い、よりよい条例づくりに結びつけていきたいと考えています。
日時 2015(平成27)年5月17日(日)13時30分から
場所 大分市大手町 大分県自治労会館 4階 大会議室
内容 第1部 大分県「条例素案」と私たちの修正案
第2部「別府市『ともに生きる条例』を制定して」(仮題)
●会場は大分県庁の東側になります。
●車の場合には周辺の有料駐車場(大手町駐車場等)をご利用ください。
「だれもが安心して暮らせる大分県条例をつくる会」第3回総会の報告
条例づくりは今年(2014年)に入って大きく進展しました。
3月県議会では、県条例をつくる会が提出した請願が全会一致で採択され、県執行部が具体的な作業(庁内検討会議の設置・団体アンケートの実施・条例検討協議会の設置など)を開始しています。
県条例をつくる会としても、6月14日に大分県総合社会福祉会館で第3回総会を開催し、1200人を超す障がいがある人とその家族の声をもとにしながら進めてきた条例づくりの意義を再確認し、条例案に込められた思いを語り合い、条例ができることで何がどのように変わるのか、どう変えていくのかを話し合いました。
報告をニュースレター「わたしも あなたも」第13号に掲載しています。
「だれもが安心して暮らせる大分県条例案」の作成
「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる取り組みにご参加、ご協力いただいておりますことに心より感謝いたします。
“私たちの条例案”を作成いたしました。
≫だれもが安心して暮らせる大分県条例案(TEXT版)
-
また「条例案」の全文(印刷版)をご希望の方にお送りします。
事務局までご連絡下さい。
「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる会について
この会は、大分県において障がい者への差別をなくし、障がいのある人もない人もともに安心して暮らせる地域をつくるために、「だれもが安心して暮らせる大分県条例」を制定するための活動を行うことを目的としています。
「だれもが安心して暮らせる大分県条例」をつくる会の取り組み内容
条例づくりの進め方
事例聴き取り → 条例案づくり → 意見募集 → 県議会提出
県条例をつくる会は世話人会を中心に運営されています。具体的な取り組みは作業チーム(6つの地域版・条例づくり班)を作って進めてきました。「地域班」を中心に2012年6月までアンケートと聴き取りを行い、寄せられた声をもとに「条例づくり班」が「条例骨格案」を作成して、意見交換を重ねた上で、2013年3月2日の臨時総会で「条例素案」をまとめました。この「条例素案」を広く県民に知らせながら、寄せられた21258筆の請願署名を12月県議会に提出。2014年3月議会で全会一致で請願が採択され、今後、大分県、県議会と「つくる会」とで、条例の具体的な検討が行われることになっています。